information
infomore- 2023.11.09
- 24h -action- 開催
- 2013.12.12
- 作家蔵報告に写真追加
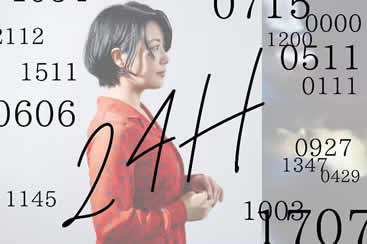 24h-action-
24h-action-
「作家×酒造蔵」温故知新の多角的文化活動
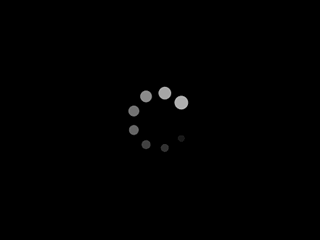
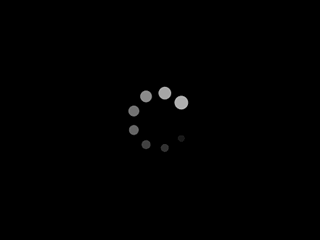
時を重ねる事により生まれた空間「蔵」。
その価値ある空間の中で、十組程度の表現者が表現を繰り広げます。
表現者は「その空間に根ざしたコンセプト」というルールで制作・表現し、「蔵」という空間とコラボレーションします。
十組程度の表現者の「それぞれのコラボレーション」により、「蔵」という空間が新しい価値を持った空間に生まれ変わります。
これは、既存の古い建造物の再利用といった観点からだけでなく、「既存の古い建造物を媒体とした文化活動」といった面からも有益であると考えております。
参加表現者は、絵画、書、立体、インスタレーション、音楽、身体表現といった一般に馴染みの深い「芸術」と呼ばれる表現分野に限らず、「生きがいの表現」など、形態にとらわれずに表現活動を行います。
また、帆足本家酒造蔵が酒蔵であることから、サブタイトルに「酒造りの工程」の名前が付けられております。毎回、そのサブタイトルにちなんだ全体テーマを設定し、特別企画として会に盛り込まれるのも特徴の一つです。
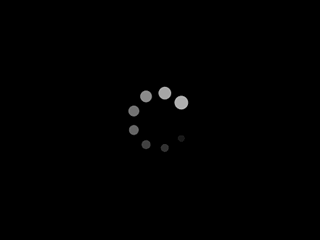
将来的には帆足本家酒造蔵内での活動から、町並みを包括したようなアート空間へ(既存の空間、視覚にとらわれない形へ)発展していければと考えています。
帆足本家酒造蔵を始めとする大分県大分市の戸次の町並みは、その可能性を描きやすい価値ある空間であると考えています。
平成18年より年に1回から2回(春と秋)、大分市戸次本町の帆足本家酒造蔵で開催していました。
平成21年度は「大分市あなたが支える市民活動」の助成を得て活動を展開し、秋には「大分県民文化祭~若者文化イベント~」として開催しました。
次回「作家蔵」開催のご案内
作家蔵は全12工程を終え、ひとまずの大団円を迎える事が出来ました。
2006年の第1回から足掛け7年の長きに渡り開催して来れましたのも、ひとえに毎回ご来場いただける皆様、戸次の皆様方、大分市や各メディアの皆様方の、温かいご協力・ご支援があったからこそ、と実行委員会一同ただただ感謝の思いでいっぱいです。
継続して欲しいとの皆様方からの温かいお言葉も沢山いただき、愛されるイベントとして開催し続けられた事を誇りに思っております。
終了について実行委員会一同色々と話し合いもいたしましたが、作家蔵として活動を始めて7年間で築き上げてきた表現の軌跡を『完結したひとつの形』として残し、作家蔵としては終了という形を取らせて頂く事にいたしました。
この作家蔵公式Webサイトは、今後もその完結したひとつの形、7年間の各アーティストの表現の軌跡、ご来場頂きました皆さんとの思い出の共有の場として残す事となりましたので、ふとした時に訪れて頂けましたら幸いです。
現在は都合上掲載写真の少ない開催会がある作家蔵報告へも、不定期で写真等を増やしたり、戸次の情報等を掲載していけたら…とも予定をしております。
もし更新を行った際は作家蔵公式X(旧Twitter)でこっそりつぶやきますので、ご都合よろしい時にゆるりとご覧いただけましたら幸いです。
皆様、本日までお力添え頂き、温かく見守って頂きまして、本当にありがとうございました!!
酒造りの工程と共に記す 表現の軌跡
2006年10月22日(日)に開催された記念すべき第1回目の作家蔵vol.1「田植」。すべてはここから始まりました。
酒蔵の空間・雰囲気、持ち味に共感した様々なアーティストが、酒蔵の持ち味を生かした表現を繰り広げました。
第1部13:00~15:00、第2部15:30~17:00の二部構成で開催され、規模は大きくありませんでしたが、表現者も見に来ていただいた方々も、酒蔵の持っている場の力をじゅうぶんに堪能していただけたイベントとなりました。
2007年4月15日(日)に開催された作家蔵vol.2「刈入」。 第1回参加者に続き、新しい表現者を加えつつ、当日飛び入り参加のアーティストも登場。 さらなる「酔い」をみなさまにお届けしました。
作家蔵vol.1同様、第1部13:00~15:00、第2部15:30~17:00の二部構成で開催されました。
この作家蔵vol.2「刈入」は反省点の多いイベントとなり、作家蔵実行委員会ならびに参加アーティスト一同、今後の展開をより深く考え、気合いを入れなおす機会となったよいイベントでした。
2009年3月8日(日)に開催された作家蔵vol.3「精米」。 この回は、通常「作家」と呼ばれる人達だけではなく、己の道に「魂」を込めた生き方をしている人達も加え、その「生き様」を発信いたしました。
83歳で初めて絵筆を握り、99歳で命尽きるまで描き続けた孤高の水彩画家「東勝吉(ひがし かつきち)」の生涯最後の半年に迫ったドキュメンタリー映画。
「ベビーマッサージ」という小さな輝く命に出会う日々。いのちの大切さと、その重要性を伝えて活動するセラピスト佐藤優美さん。
十年前にハワイで出会ったウクレレと保育や介護の現場で出会った人々。あたたかな想いを持って生きる曽我郁さん。など「魂」の「生き様」を感じることのできるイベントとなりました。
またこの回の作家蔵より、ご来場いただいた方々へテーマに沿った「お土産」をお渡しするようになり、作家蔵vol.3「精米」は「精米・生き様は食から・食は人を良くする」といったイメージから「無洗米1合」をお土産といたしました。
2009年10月17日(土)に開催された作家蔵vol.4「洗米」。 この回は当初18日(日)に開催する予定が、諸事情により土曜日に開催することになった回です。
初の土曜日作家蔵。 最初不安でいっぱいでしたが、とても多くの方にご来場いただきました。 御多忙な中お越しいただいた方々、本当にありがとうございました。
この回は大分大学JAZZ研の方々や、エレキギターでの弾き語りという異色のたっつーなど、またまた新しい顔ぶれでお送りすることができました
また、米油を主成分に米ぬかを混入してアーティストが手造りしたお土産の作家蔵特製「米石鹸」はとても好評で、良い記念になりました。
米石鹸作りをご教授いただき、作り方を手取り足取りレクチャーしていただいた日出の赤井田先生、本当にありがとうございました。
2010年3月14日(日)に開催された作家蔵vol.5「蒸米」。 サブタイトル「蒸米」の名の通り、米を強力な蒸気で蒸す作業に因んで、「高温の蒸気が広がる様」をイメージとして、「こだわり(=熱)が広がる」をテーマに開催致しました。
この回の作家蔵では「会場全体の雰囲気作り」に力を入れ、yasuさん、yoshiさん率いるoita art photographyの参加もあり、今までにない雰囲気作りをすることができました。
またお土産としては「戸次ごんぼの会」の皆様よりご協力を得て、戸次の知る人ぞ知る名物「ごぼまん」をみなさまに堪能していただくことができました。 戸次ごんぼの会の皆様、ご協力いただき本当にありがとうございました!
2010年10月31日(日)に開催された作家蔵vol.6「麹」。 『麹』により「化学変化」が起こり、お酒へと変化していく。 その様なイメージのもと、「新化」をテーマとして開催されました。
この回の作家蔵では、戸次本町「街づくり推進委員会」主催の「よいやかがり火」と相乗開催し、「よいやかがり火」で使用される手作り灯篭を作家蔵へ設置したり、参加アーティストがオリジナルの灯篭を制作するなど、会場の雰囲気もより一層増しました。
また、10月31日の作家蔵終了後も、翌週11月7日の「よいやかがり火」まで展示部門を継続展示、「よいやかがり火」前日の11月6日には作家蔵スピンオフ&よいやかがり火プレイベント「灯幻響」を開催するなど、依然とは違ったチャレンジをしました。
お土産としては「臼杵市カニ醤油」様のご協力を得て、普段手にすることの少ない「生の『麹』」をみなさまにお持ち帰りいただきました。 臼杵市カニ醤油様、ご協力いただき本当にありがとうございました!
2011年3月27日(日)に開催された作家蔵vol.7「酒母」。 下準備を終え、いよいよ「お酒」のもとが完成、つまり「お酒」というもののある意味最初。
この回の作家蔵では、『蔵からまちへ』の最終目標を具体的に形にするための最初のステップとして位置付け、『愛着の深化』をテーマにして開催されました。
アーティストそれぞれが持つ「蔵への愛着」「戸次の町への愛着」。これをそれぞれの得意とする表現で、様々な形で、様々な音で、色で、アウトプット致しました。
また戸次ごんぼの会様のご協力をいただき、お土産として「スティックごぼ天」を、そして会場にて戸次の名産「ごぼまん」「鮑腸(ほうちょう)」を、ご来場のみなさまにご堪能いただきました。 戸次ごんぼの会様、たび重なるご協力、本当にありがとうございます!
当日会場にてご堪能いただけた戸次の名産、「戸次ごんぼの会」の皆様よりご協力を得て販売された、現在全国規模で話題沸騰中の戸次B級グルメ「ごぼまん」と、同会の新商品「スティックごぼ天」、ならびに、「戸次鮑腸(ほうちょう)保存会」の皆様よりご協力を得て振る舞われた、大分県民ならだれもが知っている幻のつけ麺的な伝統の味「鮑腸(ほうちょう)」をご紹介いたします。
第8回のサブタイトルは『醪』、「醪(もろみ)」は、酒などの醸造で、原料の混合したもの、また、それを熟成させたものを言います。
これから粕を絞り、本格的に「お酒」へと変わる前段階。ある意味、一番、わくわくする時かもしれませんね。
そこで、「ありのままのものが合わさることで、わくわくした状態になる」(作家蔵専門用語で「醪(もろみ)る」)というコンセプトで、アーティスト達が混ぜ合わさって生まれる熟成された作家蔵をお楽しみいただく事を目標に開催されました。
この会の作家蔵から「蔵からまちへ」もいよいよ熟成に向け、一歩を踏み出しました!
よいやかがり灯への、灯篭制作参加に加え、「杏の会」とのコラボ企画「スタンプラリー」を開催いたしました。
第9回のサブタイトルは『上槽』、酒造りの工程において「お酒」と「酒粕」にわかれる工程のことを言います。
「研ぎ澄まされた酒」とその「絞り粕」。そのどちらも価値あるもので、それぞれ味が違います。
そこから、『ふたつの価値あるものが存在しなければ成り立たないひとつのもの、あるいは、こと』とイメージし、「ひかりとかげ」というサブテーマのもと開催されました。
また「上槽」は、より熟成にむけて洗練される工程でもあります。アーティストの作品も「より洗練された物」を目指して制作いたしました!
お土産の「酒粕クッキー」は、参加アーティストが「レシピ」「金型」「制作」などすべてにおいて手造りし、来場していただいた方々にとても喜んでいただけました!
第10回のサブタイトルは『貯蔵』、酒がしぼりだされて、じっと、慎重に待ちながら熟成していく工程です。
ためて、ピーンと張り詰めてその中で呼吸をしながら生きている。
そんな「静の中の動」を表現しながらわくわく感をつくっていけるとよいなという思いから、『まゆ』というサブテーマのもと開催されました。
『蔵からまちへ』の基本構想の元、戸次の方々と今までより一層力を合わせて地域の活性化を目指し、戸次「杏の会」様にご協力いただきまして、天然の杏から完全に手作りされた特製「あんずジャム」をお土産にさせていただきました。
第11回のサブタイトルは『樽詰』、酒の味を調整し、もう一度火入れをしてから木香をつける為に木樽に酒をいれ、銘柄商標を刷り込んだ化粧菰を巻き、縄をかける工程です。
出荷前のできあがった状態は、帯をしめて、一張羅を着て出発する前の緊張感を想像させます。
そんな気を引き締めて出発する前の緊張感を表現できたら、という思いから、『オビシメ、イッチョウラ』というサブテーマのもと開催されました。
最終回一歩手前、参加アーティストの『帯をしめ』た取り組みをお楽しみいただけた回となりました。
第12回のサブタイトルは『呑』、前回までの11工程を経て出来あがった酒を味わう工程であり、作家蔵としては、帯をしめて、一張羅を着て出発する前の緊張から解き放たれ、参加者・出演者・来場者含め楽しみ、味わう、いわば「宴」の回です。
これまでの歴史を味わう、戸次を味わう、蔵を味わう、表現を味わう、そういった幸福感に満たされることをイメージして開催されました。
作家蔵全12工程全体を通してのサブテーマ「蔵からまちへ」、まち=戸次の方々との歩みの一環として、「灯幻響with作家蔵」と題して「よいやかがり火」開催中に共催する形で、帆足本家酒造蔵中庭にて竹灯篭の灯りの中での演奏、西公園(帆足本家酒造蔵裏側の芝生広場)にてよいやかがり火の屋台と併設で作家蔵アーティストの作品販売ブースの展開等も行われました。
加えて、代表村田千尋とプロ写真家北山瑞さんによる「100人100色」というテーマで戸次の方々を中心に作家蔵に関連して頂いてきた方々に1人ずつ一輪の花を描いていただき、その絵を持った姿で撮影した写真の展示も行われ、大変ご好評を頂きました!!
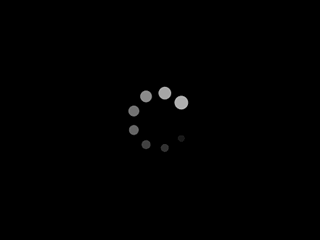 作家蔵最後のお土産は限定生産『作家蔵ミニ焼酎瓶』。
作家蔵最後のお土産は限定生産『作家蔵ミニ焼酎瓶』。
全12回の工程を経て完成した私達の「お酒」、そして皆様の中の「お酒」を詰めて頂ければ…との想いを籠めて一つ一つ制作いたしました。
またお会いできる日を楽しみに…、もちろん、賞味期限はございません。
酒造蔵と饗宴するアーティスト達
戸次の町並みをご紹介
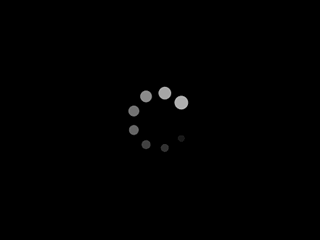
取材・記事作成 尾林祐二
帆足本家酒造蔵から戸次本町通り(日向街道)を少し北に進むと、オレンジと緑色のヒサシの懐かしい雰囲気のお店があります。
「みやべ精肉店」というお肉屋さんです。
『うちは国産の肉にこだわっちょんので~』
と明るい笑顔で、お店の女将さん。そこで買った「黒豚」が最高だったと豚星なつみ氏の力説が始まりました。
最近はほとんど見なくなった「量り売り」のお肉屋さん。
パック売りも良いですが、
『おばちゃん、すき焼き用のお肉○○グラムちょうだい。』
『あら、○○さん、今日はお客さんかい?』
『そうなんよ~。お客さんが来たら、皆ですき焼きがうちの定番やけんなぁ。』
みたいな会話が聞こえてきそうな、そんな温かくて懐かしい雰囲気のお店です。
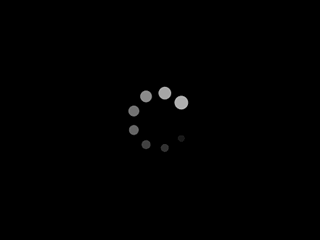
取材・記事作成 尾林祐二
みやべ精肉店の女将さん、戸次のことも詳しく、隠れたスポットを教えてくれました。
みやべ精肉店の角を曲がると、細い道路があり、100mくらい進むと小さなトタンの屋根が見えてきます。その中にお地蔵さんが鎮座しております。
このお地蔵さん、名前がわからなかったので「願掛け地蔵」と呼びますね。
このお地蔵さん、大変おしゃれ。
何と、前掛けは「コムサ(COMME CA ISM)」。
みやべ精肉店の女将さんのお話では、昔むかし、大水の際にどこからか流れてきたお地蔵さんとのこと。
大水が引いた後、今のみやべ精肉店の裏から「小豆」を洗う様な「シャッシャッシャ」という音がしよったそうな。
不思議に思った当時の住人の方が裏に回ると、このお地蔵さんがあったと。
そこで、住人の方が手厚くおまつりしたところ、「小豆」を洗う様な「シャッシャッシャ」という音も消えたとさ。
そんなお話しがあるお地蔵さんで、知ってか知らずが、願掛けに来る人も少なくないとか。
ある時、歩けなかった子どもが歩ける様になった、とお礼の前掛けがしてあるのに気づいた女将さん。今も大切にその前掛けを取ってあると話してくれました。
ちょっとの散策と思って、願掛けに行ってみてはいかがですか?
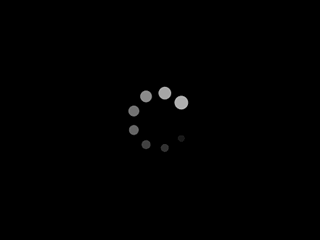
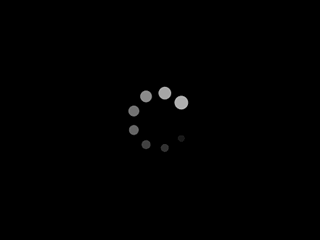
取材 豚星なつみ、記事作成 尾林祐二
さて、みやべ精肉店をあとにして、豚星なつみ氏のおススメスポットへ。
「願掛け地蔵」を少し進んだところに「妙正寺」というお寺があり、そこの一角の小さな社?に「火防せ地蔵」は鎮座しております。
以下、妙正寺の説明より抜粋します。
明治39(1906)年4月 戸次本町(当時は”市と称していた”)の中市班より発した火災は、たちまちのうちに通りの家屋に類焼していきました。
しかし火の勢いは、下市班の地蔵堂(旧大分銀行戸次支店、現冨春館駐車場)の手前で不思議なことに止まり、それから住民の間で誰かれとなくこのお地蔵様を”火防せのお地蔵様”と呼ぶようになりました。
毎年4月には下市班によるお接待が行われ、本町のみならず、近隣の子どもたちが赤飯や混ぜご飯のお握りをもらおうと地蔵堂の前に列をなしたものでした。
この行事は昭和30年代前半まで続いていました。
地蔵堂は昭和38(1963)年、大分銀行支店の拡張に伴い、妙正寺のご好意により境内の現在の現在地に移転しました。
― 2006年10月 戸次本町下市上班、妙正寺 より
作家蔵へのお問い合わせや 素朴な疑問など
「作家蔵に参加していたアーティスト情報を知りたい!」
「作家蔵に参加していたアーティストに会いたい!」
「作家蔵実行委員会に物申す!」
等々のご要望・ご不明な点などありましたら、下記お問い合わせフォームに必要事項をご入力の上 [ お問い合わせを送信 ]を押してください。
お送りいただいた内容を担当スタッフが確認してご対応させていただきます。
お問い合わせの内容によっては返信・対応にお時間をいただくことがございますので予めご了承ください。
送信後に自動返信の内容確認メールが届かない場合は、フォームシステムの不具合やご入力頂いたメールアドレスに誤りがある可能性がございますので、お手数をおかけいたしますが mail@sakkagura.com 宛てに直接お問合せください。